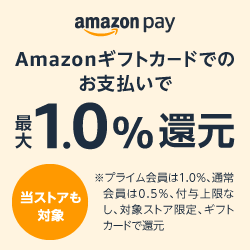- 空いているスペースを有効活用しよう!
- 棚を階段の下や出入り口の上部などに吊ると空いているスペースを有効活用することで、増えていく本や衣類を整理するための棚を増やし、収納力をアップすることができます。
棚受け家具を使う
棚受けは下地のある壁、あるいは壁の中の柱や桟といった強度のある部分にとりつけます。作業する前に構造を調べ取付けることが必要です。
最近では棚受け金具もデザインが豊富になり、L字型のシンプルなもの以外も選べます。棚受けに合わせて棚板も素材や仕上げにより素敵なインテリアを楽しむことができます。

棚受け支柱を利用する
壁全面に棚をつくるのは、大変な作業だと思いがちですが、棚受け支柱を使うと案外簡単にできます。
壁に棚柱という部材を取付けることで、そこに棚受けをはめ込むだけで、手軽に可動棚をつくれます。また、支柱を3本、4本と増やし棚を支えれば幅の広い棚もできます。可動棚はその名の通リ間隔をいつでも変えられるのも魅力です。棚の奥行きも後から自由にセットすることができます。
- 支柱を垂直にネジ止めします。壁下地の桟が横に入っていて、ネジが聞かない場合は板を打ちつけそれにネジを止めます。
- 棚受けを必要なだけセットします。このとき棚受けを差し込んだら、木ヅチなどで叩き込みます。
- 棚受けをセットしたら、棚板をその上にのせます。
キャビネットなどの棚板を増やす
- ダボを使う方法
- よくある組み立て式の棚によく使われているのがダボです。ダボの固定は、穴をあけて差し込むタイプが多いです。側板の穴にダボを埋め込み、そのダボに棚を乗せることで棚の高さを変えられるので便利です。また、ネジこみタイプのダボを使えばダボ穴がない箇所にでも簡単に棚板を取り付けることができます。
- 受け木を取り付ける方法
- 壁と壁に挟まれた場所(幅90㎝くらいまで)に棚を作る時にも使える方法ですが、側板の両側に受け木(桟)を取り付けその上に棚板をのせる方法があります。受け木を取り付けるときには、クギやネジが効くかどうか確かめましょう。中が、空洞の場合やコンクリート壁の場合は、アンカー等が必要です。また、木面であれば、接着剤で固定することも可能です。
- キャビネット等が歪んでいることがあるので必ず、手前と奥行きの高さ、幅を測っておきます。棚の高さを決めたら印をつけます。
- 受け木は、15~20厚ぐらいの角材を切ったものを使います。クギやネジを使う場合は、した穴をあけて作業するのがコツです。
- 取り付けた一方に棚板を仮にのせ、水平になる位置を確認して、もう一方の受け木を取り付けます。棚板をのせれば完成です。
鴨居や長押を利用した棚
ちょっとしたL字の隅に棚板をのせることで簡単な棚になります。廊下の隅など、幅の狭い所に棚を作るときは、切り込みを入れた板をわたし、金具で止めるだけでも十分に利用できます。
鴨居に棚をのせる
- コーナーの柱に合わせて、棚板に切り込みを入れます。
- 家具補強用の金具などを木ネジで固定すると、棚板がずれません。
- コーナーがない場合
- 棚板をのせる面が一辺だけの場合には、他辺をクサリや棚受け金具でささえます。
棚板がしなわないために
棚板の厚みが薄いと棚板がたわむことがあります。これを防ぐには、棚板の前面に幅の狭い板やアルミフレームを取り付ける方法があります。補強用の板は、普通1のように取り付けますが、高い所にある棚には、落下防止をかねて2のように付けても良いでしょう。アルミフレームは、金属用のドリルで穴をあけ固定します。
※あくまで一例のご紹介になりますのでお問い合わせいただきましても、
詳細なご案内は致しかねますのでご了承ください。
詳細なご案内は致しかねますのでご了承ください。