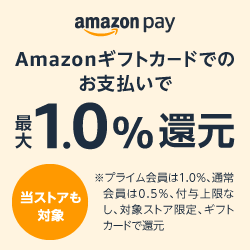種類を知って適切な商品選びを タイルの種類
タイルは、材料や焼成温度、吸水率などによって種類があり、種類によって適した使用場所、方法なども異なります。タイルの種類を学んで適切な商品選びの参考にしましょう!
タイルの種類について学ぼう!
タイルには様々な種類があり、材料や焼成温度、吸水率などによって細かく分類されます。タイルのデザインももちろん大切ですが、タイルの種類を詳しく理解することによって最適な商品を選ぶことができます!
タイルの種類の表記について
JIS規格によるタイルの分類
-

-
JIS規格ではタイルを、成形方法(A/B)と吸水率(I~III類)の組み合わせにより分類しています。この組み合わせによりタイルの特性や使用場所が異なるため、タイルを選ぶ際には、カタログや商品ページに記載されているこの分類を参考にして選びましょう。
タイルの成形方法と吸水率
によって分類されます
| 成形方法 | 強制吸水率 | ||
|---|---|---|---|
| I類(3% 以下) |
II類(10% 以下) |
III類(50% 以下) |
|
| 押し出し 成形(A) |
A I | A II | A III |
| プレス 成形(B) |
B I | B II | B III |
2008年のJIS改定により、旧規格では自然吸水率が指標とされていたのに対し、強制吸水率が指標とされるようになりました。また、磁器質/せっ器質/陶器質で分類されていたのに対し、I類/II類/III類という分類に変わっています。
それぞれの分類について詳しく見ていきましょう。
タイルの成形方法の違い
押し出し成形/湿式成形(A)
-

-
押し出し成形とは、押し出し成形機を用い、水分を含んだ粘土状の原料をところてんのように高圧で押し出して成形する方法です。水を含んだ原料を焼成するため、収縮やひずみが生じやすいですが、焼き物ならではの風合いや味を楽しむことができます。
プレス成形/乾式成形(B)
-

-
乾燥させた粉上の原料を金型に充填し、高圧によって押し固めて成型する方法です。プレス成形によって製造されるタイルは、均一な厚みや形状を持ち、高い品質と耐久性があります。安定した寸法精度で大量生産ができるため、屋内や屋外の床面、壁面など様々な用途に使用されます。
タイルの吸水率の違い
材料、焼成温度によって
吸水率が異なります
-
I類(磁器質タイル)


強度が高く、吸水率が3%以下と低いため、様々な場所で使用可能です。雨がかかる屋外での使用や、水回りでの使用にも適しています。
-
II類(せっ器質タイル)


吸水率10%以下で、内装用・外装用としても使用されます。焼き物特有の風合いを楽しめる湿式成形で製造されているものが多いのが特徴です。
-
III類(陶器質タイル)


タイルの素地が柔らかく、吸水率が高いため、基本的には内装用タイルとして用いられることが多いです。使用可能な場所をよく確認しましょう。
施釉(せゆう)の有無
施釉(せゆう)タイルとは?
-

-
施釉タイルとは、うわぐすりとも呼ばれる「釉薬(ゆうやく)」を表面に塗って焼成したタイルです。釉薬によって、タイルの表面に光沢が生まれ、様々なデザインや模様を出すことができます。また、タイルの表面をコーティングすることによって、表面からの吸水を防いだり、汚れをつきにくくするといった効果もあります。
無釉(むゆう)タイルとは?
-

-
無釉タイルとは、素焼きタイルとも呼ばれ、タイルの表面に釉薬を施さず、そのまま焼成したタイルのことを言います。無釉タイルは、表面に塗膜が無く素焼き特有の風合いや質感を持ちます。基本的に、光沢はなくマットな仕上がりになるのが特徴です。施釉タイルに比べて吸水性が高いため、水や汚れが染み込みやすいため使用場所には注意が必要です。
タイルの機能性について
耐凍害性
-

-
屋外で使用されるほとんどのタイルには、「耐凍害」という性質が備わっています。寒冷地域において、タイルの内部に浸透した水分が、凍って膨張することでタイルに圧力をかけます。耐凍害性のあるタイルは吸水率が低いため、タイルの内部の水分が凍結、融解を繰り返すことによるタイルの変形や損傷を最小限に抑えることができます。
ノンスリップ機能
-

-
ノンスリップ機能を持つタイルは、表面に凹凸があり足裏との摩擦を増加することで、歩行時の滑りを抑制します。特に屋外や水回りの床で使用するタイルは、表面に水がかかると大変滑りやすくなるため、ノンスリップ機能を持ったタイルを選びましょう。
RESTAのタイル商品
ラインナップ
屋外にも使える磁器質タイル
屋内の壁に最適な陶器質タイル
DIY向けタイルも種類豊富!
タイル教室
-
豆知識

-
施工方法

-
その他おすすめコンテンツ