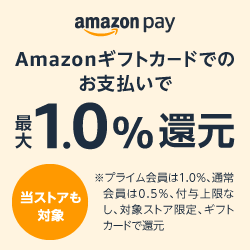網戸の歴史
網戸は、虫の侵入を防ぎつつ、風を取り入れることができる、生活必需品です。しかしつい最近までは、網戸がない生活が普通でした。今回はどうやって網戸が普及したのか、歴史から辿っていきます。
蚊帳の時代
-

-
網戸の歴史は比較的浅く、窓サッシにつける今の形状になったのは、50年ほど前と言われています。金閣寺や神社仏閣などを見てもらえれば分かるように、昔の日本家屋には、網戸はついていません。
昔の人々は、網戸ではなく「蚊帳(かや)」というものを使って虫を防いでいたようです。元々は大変高価なもので、上流階級だけの贅沢品でしたが、江戸時代には庶民にまで普及しました。
網戸の普及
-

-
昭和30年代に入り、網戸が一気に普及しました。
普及の原因の一つは、「垣内商事(いまのダイオ化成)」が、合成繊維でできた網を開発したことです。サランと呼ばれる塩ビ系の樹脂が使用されていたため、この網のことを「サラン」と呼ぶ人もいました。
もう一つの原因は、アルミサッシの普及です。窓サッシが木製からアルミ製へと急激に変化が起こると同時に、網戸の枠もアルミ製になっていきました。
こうして蚊帳は姿を消し、網戸が広まっていきました。
網戸の進化
-

-
網はどんどん進化し、様々な種類の網が登場しました。外から見えにくく中からはよく見える網戸、ペットがひっかいても破れない網戸、燃えない網戸、花粉を通さない網戸、雨が振っても入らない網戸など多種多様です。節電・エコの時代に自然の風が見直され、網戸が再び注目されることは間違いありません。
日本と海外の網戸事情
-

-
海外でも網戸は一般的に使われています。欧米では、引き戸よりも、上げ下げ窓や開き戸が多いので固定式の網戸が多く、引き違いタイプの網戸は少ないかもしれません。また、木製の建具が多いので、その枠に網を打ち付けたようなものが多い気がします。
欧米でよく見かける玄関網戸が日本であまり見かけない理由は、家に入るときに玄関で靴を脱ぐか脱がないかという文化の違いもあるようです。玄関で靴を脱がないアメリカでは、玄関は内側に開きますが、日本では内側に開くと靴が邪魔になるため、外側に開きます。その結果、日本では内側に簡単に取付けられる引き戸タイプの網戸が設置できないのです。こういった事情から、日本の玄関網戸は、横に引くタイプやロールでしまえるタイプなどが進化してきました。
網戸教室
-
購入前の準備

-
商品選びのポイント

-
網戸の使い方・コーディネート

-
お手入れ・トラブル対策

-
網戸の豆知識